最終更新日:2025/10/23
発注書の役割や作成目的、記載すべき項目を分かりやすく解説し、メール・郵送・FAXでの送付方法や保存期間・保存方法のポイントも整理しました。さらに、発注業務に多い入力ミスや情報共有の遅れといった課題を、販売管理システム導入で効率化する方法も紹介します。
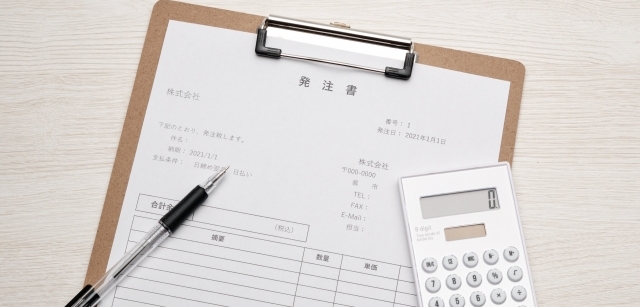
目次
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
企業間の取引では、見積書や請求書と並んで「発注書」が重要な役割を果たします。発注書は商品やサービスを正式に注文する際に発行される書類で、取引内容の確認やトラブル防止に役立ちます。
とはいえ「発注書って何を書けばいいの?どう送付・保管すればいいの?」と悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、発注書の基本から送付・保存の方法、さらには発注業務の課題解決策まで解説します。
この記事で分かること
● 発注書の概要や作成する目的
● 発注書の記載内容と送付・保存の方法
● 発注業務の課題と効率化のポイント
発注書とは?
-
発注書とは、発注側(商品やサービスを注文する側の企業)が受注側である取引先の企業に対し、正式に「発注します」という意思を示すために発行する書類です。「注文書」と呼ばれることもありますが、基本的にはどちらも同じものを指します。
発注書には発注内容や数量・金額、納期といった取引条件を明記し、双方の認識を一致させる役割があります。発注書を受け取った受注側は、その注文を引き受ける証拠として「発注請書」を発行し、これらの書類をもって契約成立となります。
このように、発注書は受発注の証拠となる重要書類です。特に下請取引に該当する場合には、親事業者(発注者)は発注書の交付が義務付けられているので注意しましょう。
発注書を作成する目的
-
発注書を発行する主な目的は、大きく分けて3つあります。
● 注文の意思を明確に示すこと
● 取引条件を双方で確認すること
● 事務処理を円滑にすること以下では、それぞれの目的について解説を加えます。
注文の意思を示す
-
企業間取引では、口頭の約束だけではなく書面で正式に注文の意思を示すことが重要です。発注書を先方に送付すること自体が「貴社の商品・サービスを正式に発注します」という明確な意思表示となります。書面による発注の意思表示があれば、受注側も安心して業務を進めることができ、行き違いを防ぐ効果があります。
発注書は発注側の申込み意思の証拠ともなるため、受注側にとっても安心材料となり、より信頼性の高い取引ができます。
取引内容を確認する
-
発注書には発注内容や条件を詳細に記載します。これにより、発注側と受注側双方で取引条件の最終確認が可能です。例えば、数量・単価・納期・支払条件などを発注書で改めて書面化し、見積書の内容と照合することで認識違いがないかをチェックできます。口頭のやり取りだけでは「言った/言わない」「聞き間違い」などのトラブルが起こり得ますが、発注書で条件を明文化しておけば無用な紛争を防止できます。
このように、発注書は取引条件をズレなく共有する手段となり、後日の齟齬やクレームを未然に防ぐ役割を果たします。
事務処理を円滑にする
-
発注書を発行することは、社内外の事務処理をスムーズに進めるのにも役立ちます。書面で発注内容を残すことで受発注の業務フローが可視化され、関連部署間で情報共有しやすくなるためです。例えば、発注書ごとに発注番号を付与して管理すれば、後日請求書や納品書と照合しやすくなり、経理担当者も迅速に処理できます。
発注書の記載内容
-
発注書には、取引に関する基本事項をもれなく記載する必要があります。明確な書式の定めはありませんが、一般的に以下のような項目を含みます。
自社でテンプレートを用意する際は、下記のうち必要な項目が記載されているかを確認しましょう。
項目 説明 タイトル 書類の最上部に「発注書」または「注文書」と明記します。受け取った相手が一目で発注書だと分かるよう、大きめの文字で記載します。 発注先(宛名) 発注先となる取引相手の会社名・部署名・担当者名を記載します。会社宛ての場合は末尾に「御中」、個人名宛ての場合は「様」を付けるのがマナーです。 発注書番号・発注日 発注書固有の番号と発行日を記載します。同一案件で発行する見積書・請求書などと統一の番号にしておくと、後日の管理や問い合わせ対応が容易になります。発注日は実際に発注書を発行した日付を記入します。 発注内容 発注する商品・サービスの名前を記載します。できるだけ分かりやすい正式名称を使い、略称や俗称は避けます。 発注元情報 発注者の会社情報として、会社名・住所・担当部署・担当者氏名・連絡先などを記載します。会社として正式な発注であることを示すため、社判や担当者印を押印するケースもあります。 金額 発注金額を税抜金額と消費税額、税込合計額に分けて記載します。特に税込合計金額は相手が一目で認識できるよう太字にするなど強調します。発注金額は見積書の金額と一致しているか必ず確認しましょう。 納期・支払条件 発注する商品の納品希望日や、代金の支払い条件を記載します。下請取引の場合、支払サイトは法律上「納品後60日以内」と定められているため、60日を超える支払期日を記載しないよう注意が必要です。 有効期限(任意) 有効期限を設ける場合は記載します。ただし通常、発注書は発行後すぐ発注処理に入るため必須項目ではありません。 備考(任意) 上記項目以外に特記すべき事項があれば記載します。 各社や業界でフォームは多少異なりますが、形式にかかわらず取引条件を網羅するという点が重要です。また、発注書に収入印紙を貼る必要は通常ありません。契約書としての性質を持つ場合には印紙税法上の課税文書となり得ますが、電子データで発行する場合は印紙税非課税です。
発注書の様式は自社で工夫できますが、基本項目に漏れが無いようあらかじめテンプレートを用意しておくと安心です。
発注書の送付方法
-
発注書を取引先に送付する方法としては、大きく分けて「メール」「郵送」「FAX」の3つがあります。
どの方法でも問題なく発注は成立しますが、それぞれにメリット・デメリットや注意点があります。自社および取引先にとって適した送付方法を選びましょう。
メールで送付する
-
現在、発注書をメールで送付する方法が主流となっています。多くの場合、WordやExcelのままでは改ざんリスクがあるため、PDFに変換して添付するのが基本です。社判や押印は必須ではなく、必要に応じて電子印影を利用したり、印刷後に押印してスキャンしたデータを送る方法もあります。
メール送付の際は、件名に「発注書送付の件」と明記し、本文にはあいさつ文と発注内容の概要を簡潔に記載しましょう。これにより相手が見落とさず、内容確認をスムーズに進められます。また、送付前に相手企業がメールでの注文を受け付けているか確認し、送付後には電話などで確認を取ると確実です。
メリットは、即時性とコスト削減です。送信ボタン一つで相手に届き、郵送代や印刷代も不要です。送信履歴が残るため、証拠保全性も高まります。一方で、デメリットとしては相手がメールを見落とすリスクや、電子取引データとして適切に保存しなければ税務上の問題になる点があります。電子帳簿保存法に基づくルールに従い、保存方法を整備することが求められます。
郵送で送付する
-
郵送は従来から行われている方法で、発注書の原本を届けられるため信頼性が高いのが特徴です。受け取った相手に「正式な発注書」として扱ってもらいやすく、確実に目を通される点も大きなメリットです。
ただし、発注書は法律上「信書」に該当するため、郵便や信書便を使う必要があります。宅配便やメール便では送れないので注意してください。発注書を送る際は、A4対応の封筒を準備し、宛名には「御中」や「様」を正しく使い分けます。封筒には「発注書在中」と朱書きしておくと親切です。また、添え状を同封するのが慣習で、あいさつ文と「発注書を同封しましたのでご査収ください」といった文面を添えると良いでしょう。
郵送は原本性と信頼性が魅力ですが、到着まで数日かかることや、切手代や印刷代といったコストがデメリットです。郵便事故のリスクもゼロではありません。緊急時には、まずメールやFAXで送付し、その後郵送で原本を送る「二段構え」の対応が実務ではよく用いられます。
FAXで送付する
-
FAX送付は、紙の発注書を即座に送れる点が強みです。特に緊急時や営業時間外でも相手のFAXに届くため、スピード感を重視する場面で利用されます。
一方で注意すべきは、宛先番号の誤入力による誤送信です。誤送信は機密情報の漏洩につながるため、番号を事前に確認し、可能であれば電話帳登録やQRコード送信を活用しましょう。また、送信前に相手に「これから発注書をFAXします」と連絡しておくと、受信トレイで埋もれるのを防げます。
FAX送付の際は送付状(カバーページ)を添えるのがマナーです。宛名、件名、送信枚数、簡単なあいさつ文を記載し、受信者が内容を把握しやすいようにします。送信後は電話などで受信確認を取り、必要に応じて原本を郵送するかどうかも相手企業に確認しましょう。
発注書の保存期間
-
発注書は、取引の証拠となる「証憑書類」の一つとして、税法や会社法で保存が義務付けられています。取引の透明性を保ち、税務調査や監査に対応するため、定められた期間きちんと保管しておくことが重要です。
法人の場合、発注書を含む取引書類は原則7年間保存する必要があります。起算日は事業年度の確定申告書提出期限の翌日からであり、青色申告で欠損金が発生した年度については10年間に延長されます。これは法人税法などで定められており、経理や契約管理に関わる重要なルールです。
一方、個人事業主の場合は原則5年間の保存義務があります。こちらも青色申告・白色申告を問わず、確定申告期限の翌日から起算します。帳簿や契約書、見積書と並んで発注書も対象となり、税務署から提示を求められる場合があります。
保存義務を怠った場合、税務調査で必要な証拠書類を提出できず、経費計上が認められない、あるいは売上の裏付けが不足すると判断される恐れがあります。その結果、追徴課税や加算税を課されるケースもあります。
発注書は単なる事務書類ではなく、契約条件や取引履歴を証明する重要な記録です。特に建設業など一部業界では、工事関連書類の長期保存義務が設けられている場合もあります。こうした背景からも、発注書は取引証憑として厳格に扱うべき文書といえるでしょう。
保存期間は「原則」であり、法改正や業種特有の規定によって変わる可能性があります。運用にあたっては、必ず税理士や専門家に確認し、自社に適した保存ルールを整備しておくことが安心です。
発注書の保存方法
-
発注書の保存方法には、大きく分けて「電子保存」と「紙保存」の2種類があります。電子帳簿保存法の改正により電子保存が広がっていますが、紙での保存も依然として用いられています。それぞれにメリットとデメリットがあり、企業規模や業務フローに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
電子データとして保存する
-
発注書を電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法に基づいた対応が求められます。この法律では、保存データに真実性と可視性を確保することが条件とされています。真実性の確保には、タイムスタンプの付与や訂正削除履歴が残るシステムの利用が有効です。可視性の確保では、取引日・金額・取引先名などで検索できる機能を備える必要があります。
これらの要件を満たさないと、青色申告の承認取消といった不利益を受ける可能性があるため注意が必要です。特に2022年の改正以降は、メールで受け取った発注書PDFなども電子データとして保存することが義務化され、猶予措置も終了しています。
電子保存のメリットは、紙を保管する必要がなく、省スペース化につながる点です。また、検索性が高いため過去の取引履歴を迅速に確認でき、クラウド保存を利用すればバックアップや災害対策も容易です。一方で、システム障害や誤操作によるデータ消失のリスクもあるため、定期的なバックアップを複数拠点に確保しておくことが推奨されます。
電子保存は効率化に大きく貢献しますが、制度対応は複雑です。具体的な運用方法は税務署や専門家に確認しながら、自社に合った保存ルールを整備することが大切です。
紙で保存する
-
発注書を紙のまま保存する方法は、従来から行われている基本的な手法です。受発注の証拠として受け取った原本や、自社発行分の控えを整理・保管しておくことで、税務調査などの際に迅速に提示できます。
整理方法としては、取引先別や年月別にファイリングする、発注番号や件名で索引を付ける、といった工夫が有効です。保管場所は鍵付きキャビネットや書庫を利用し、劣化や紛失を防ぐために防水ファイルや耐火金庫を活用するのも良いでしょう。原本を動かさずにコピーやスキャンを回覧用に使うことで、紛失リスクを減らせます。
紙保存のメリットは、原本をそのまま保持できる安心感と証拠性の高さです。監査や調査の場面でも信頼性が高く、紙媒体に慣れた担当者にとっては扱いやすい面もあります。また、必要に応じてメモを書き込める柔軟さも魅力です。
一方で、デメリットは保管スペースの圧迫や検索に手間がかかる点です。さらに、経年劣化や火災・水害といったリスクも伴います。そのため、最近では紙保存と電子保存を併用し、スキャンデータをバックアップする企業も増えています。紙保存を選ぶ場合も、整理と安全管理を徹底することが求められます。
発注業務の課題は販売管理システムで解決できる
-
従来の発注業務では、Excelや紙の伝票、FAXなど手作業中心の管理が一般的でした。しかし、この方法では転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが起こりやすく、処理に時間がかかることも少なくありません。特に同じ情報を見積書、発注書、請求書に繰り返し入力する作業は非効率で、担当者の負担を大きくしています。
また、部門間で情報共有が遅れると、在庫不足や二重発注といったトラブルにつながります。「この注文は処理済みか」「在庫は足りているか」と確認に時間を取られ、結果として納期遅延や信用問題に発展することもあります。
こうした課題は、販売管理システムを導入することで大きく改善できます。システム上で見積から発注書を自動作成できれば、二重入力を防ぎ、処理スピードが飛躍的に向上します。さらに、リアルタイムで情報が更新されるため、営業部・購買部・経理部など関係部署で最新データを共有でき、業務の抜け漏れを防げます。
在庫や納期管理の精度も向上し、過剰在庫や欠品リスクを減らせます。帳票のPDF発行やメール送信機能を備えるシステムなら、紙書類の整理や郵送作業も不要になり、電子保存にも自然に対応可能です。加えて、承認ワークフロー機能により、不正発注の抑止や内部統制の強化にも役立ちます。
特にクラウド型販売管理システムであれば、インターネット環境さえあればどこからでも利用可能です。複数の担当者が同時にアクセスできるため、テレワーク環境にも適しています。たとえば「s-flow」では、見積から請求までの帳票をクラウドで一元管理でき、発注書の自動作成や電子保存にも対応しています。これにより、紙やExcelでの煩雑な管理から解放され、付加価値の高い業務に集中できるようになります。
まとめ
-
発注書は、企業間取引において欠かせない書類です。正式な注文の意思表示であり、取引条件を確認し、事務処理を円滑にする役割を果たします。発注書の記載内容には必須項目があり、送付や保存の方法にも注意が必要です。メール・郵送・FAXといった送付手段にはそれぞれの特徴があり、電子保存と紙保存の双方にメリットとデメリットがあります。
一方で、従来の発注業務は手作業中心で、入力ミスや情報共有の遅れといった課題が発生しやすい点も見逃せません。これらの課題は、販売管理システムの導入によって効率的に解決できます。システム上で見積から発注書を自動作成でき、リアルタイムで情報共有が可能になることで、発注業務全体の精度とスピードが向上します。
クラウド販売管理システム「s-flow」は、見積・発注・請求といった一連の帳票をクラウド上で一元管理できる仕組みを提供しています。紙やExcelに頼らず、発注業務を効率化し、管理コストを削減できる点が大きな魅力です。この記事をきっかけに、自社の発注業務を見直し、よりスムーズで信頼性の高い体制を整えてみてはいかがでしょうか。

- クラウド販売管理システム【s-flow】コラム編集部
- s-flowのコラムでは、販売管理・受発注管理・在庫管理・入出金管理をはじめとした各業務や管理に関連する「お役立ち情報」をご紹介しております!








