最終更新日:2026/01/15
ビジネスの現場では、商品やサービスの受け渡しに欠かせない書類として「納品書」と「請求書」があります。どちらも取引の証拠となる重要な書類ですが、目的や記載内容、発行のタイミングなどに明確な違いがあります。これらを混同すると、支払い遅延や経理処理のミスなど、取引上のトラブルにつながる恐れもあります。
本記事では、納品書と請求書それぞれの役割と違いをわかりやすく解説するとともに、関連する見積書・領収書の位置づけ、さらに電子化が進む背景までを詳しく紹介します。取引の流れを正しく理解し、スムーズな業務処理に役立てましょう。
この記事で分かること
● 納品書と請求書の基本的な役割と違い(目的・記載内容・発行タイミング)を理解できる
● 見積書・領収書を含む「取引書類4大書類」の関係性と使い分けを整理できる
● 納品書・請求書の電子化が進む背景と、効率化・セキュリティ向上につながる最新の対応策を学べる
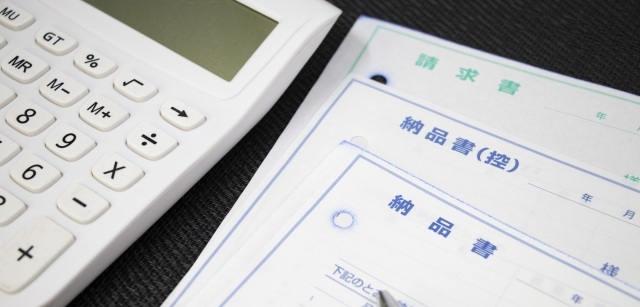
目次
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
納品書と請求書、それぞれの役割とは?
-
ビジネス取引では、商品やサービスの受け渡しに関するやり取りを正確に記録し、誤解やトラブルを防ぐことが求められます。その際に重要な書類が「納品書」と「請求書」です。どちらも取引の証拠となる点では共通していますが、目的や役割は異なります。
ここでは、それぞれの意味と役割を整理して解説します。
納品書は「商品の内容証明」
-
納品書は、商品やサービスを確かに納品したことを証明するための書類です。発注側(買い手)はこの書類をもとに、注文した内容と実際に納品された内容が一致しているかを確認します。
納品書には、品名・数量・単価・納品日などが明記され、取引先同士の認識を一致させる役割を果たします。これにより、納品ミスや数量違いといったトラブルを未然に防ぐことができます。
法的に発行義務はありませんが、ビジネス上の信頼関係を保つうえで欠かせない書類といえるでしょう。多くの企業では、納品完了の証拠として納品書を発行し、控えを自社で保管しています。
請求書は「代金の支払い依頼」
-
請求書は、納品済みの商品やサービスに対して代金の支払いを求めるための書類です。発行するのは受注側(売り手)であり、支払期限・金額・振込先などが明記されます。
請求書は単なる支払い依頼にとどまらず、取引が実際に行われたことを証明する重要な書類でもあります。経理処理や税務申告の際にも必要となるため、正確な記載が求められます。
納品書と同様に法律上の発行義務はありませんが、税務上の証拠書類としての役割を持つため、企業では請求書の発行・保存を徹底するのが一般的です。正確な請求書のやり取りは、支払い遅延や金額誤りといったトラブル防止にもつながります。
納品書と請求書の3つの違い
-
納品書と請求書はどちらも取引に欠かせない重要書類ですが、役割や作成のタイミング、記載内容には明確な違いがあります。混同すると支払いや確認業務に支障をきたすこともあるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、代表的な3つの違いを整理して紹介します。
送付するタイミング
-
最も分かりやすい違いは、送付するタイミングです。
納品書は、商品やサービスを納品する際に一緒に送付します。これは、発注内容と納品内容が一致しているかを取引先に確認してもらうためです。納品書が同封されていることで、受け取る側はその場で検品や確認ができ、ミスや数量違いの早期発見につながります。
一方、請求書は納品後に送付するのが一般的です。納品内容が確定した後、代金の支払いを正式に依頼する目的で発行されます。多くの企業では、月末や月初などの締め日に合わせてまとめて請求書を送付しています。
作成する目的
-
納品書の目的は、納品内容を証明し、取引先と納品状況を確認することです。契約どおりに商品やサービスが提供されたかを双方で確認することで、誤納品や数量間違いといったトラブルを防ぎます。
対して請求書の目的は、納品した内容に基づいて代金を正式に請求することです。請求書は金銭の授受に関わる重要書類であり、経理処理や税務申告にも必要となります。したがって、金額・消費税・支払期日などを正確に記載することが求められます。
記載される項目
-
納品書には、納品された商品やサービスの内容を明確にするための項目が中心に記載されます。具体的には、品名・数量・単価・納品日・取引先情報などです。これらの情報は、発注内容との照合に使われます。
一方、請求書には支払いに関する情報が詳しく記載されます。請求金額の総額、支払期限、振込先、請求日などが代表的です。さらに、請求内容の内訳として納品明細も含まれます。請求書は、取引内容の証拠となると同時に、支払いを円滑に進めるための実務的な役割も担っています。
納品書と請求書はどちらか片方でよい?
-
取引書類にはさまざまな種類がありますが、「納品書」と「請求書」を両方発行するべきか、それともどちらか片方でよいのか迷う企業も多いでしょう。結論から言えば、状況に応じて使い分けが可能ですが、請求書は原則として必ず発行すべき書類です。ここではその理由と、両書類をまとめて発行するケースについて解説します。
請求書は原則として必要
-
請求書は、代金の支払いを正式に依頼するための根拠となる書類です。法律上、発行が義務付けられているわけではありませんが、支払い請求の正当性を証明する「証拠書類」として重要な役割を持ちます。特に企業間取引では、支払い内容や期日を明確にし、トラブルを防ぐために必ず請求書を発行するのが一般的です。
また、2023年に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、「適格請求書発行事業者」として登録している企業は、取引先に対してインボイスを交付する義務があります。このインボイスは、実質的に請求書と同じ役割を果たすものであり、消費税の仕入税額控除を受けるためにも欠かせません。
したがって、法的義務がなくとも、経理・税務上の観点から請求書の発行は実務上必須といえるでしょう。
納品書兼請求書としてまとめるケースもある
-
一方で、取引の内容によっては「納品書兼請求書」として一つの書類にまとめるケースもあります。たとえば、納品と同時に代金の請求が完了するような取引(現金取引・単発の業務委託など)では、納品書と請求書を一体化することで手間を省くことが可能です。
この形式には、発行コストの削減や事務処理の効率化といったメリットがあります。ただし、インボイス制度に対応する場合は、請求書の要件を満たす必要があります。具体的には、登録番号・税率・消費税額など、適格請求書に必要な項目がすべて記載されていなければなりません。
また、取引先によっては「納品書と請求書を別で受け取りたい」と指定している場合もあるため、書類の形式は事前に相手方と確認しておくことが重要です。
納品書と請求書以外の重要書類は?
-
取引業務では、納品書や請求書のほかにも、取引を円滑かつ正確に進めるために欠かせない書類がいくつかあります。代表的なのが「見積書」と「領収書」です。これらは、納品書・請求書と並び「4大書類」と呼ばれ、取引の始まりから完了までを一貫して支える重要な役割を担っています。それぞれの目的と特徴を見ていきましょう。
見積書
-
見積書は、受注者(売り手)が発注者(買い手)に対して、提供できる商品・サービスの内容や金額、納期などを提示する書類です。取引の初期段階で発行され、双方の認識を合わせるための重要なコミュニケーションツールとなります。
主な目的は次の2つです。
● 取引内容の確認:見積書をもとに、提供内容・数量・金額・納期などの条件を明確にし、誤解やトラブルを防ぎます。
● 発注の検討材料:発注者は複数の業者から見積書を取り寄せ、価格やサービス内容を比較検討します。これを「相見積もり」と呼び、コストと品質のバランスを判断する際の基準となります。なお、見積書自体には法的拘束力はありません。
ただし、見積書の内容をもとに正式な発注が行われた場合、その条件が契約内容とみなされ、契約が成立します。したがって、金額や条件の記載は慎重に行う必要があります。
領収書
-
領収書は、代金の受け渡しが完了したことを証明する書類です。支払いが完了した際に受注者(売り手)が発行し、発注者(買い手)が受け取ります。
主な目的は以下の通りです。
● 支払いの証明:領収書は、取引先から確かに代金を受け取ったことを示す証拠書類となります。二重払い防止の役割も果たします。
● 経費精算の証憑:買い手側では、経費計上の際の正式な証拠(証憑書類)として使用されます。
● 内部不正の防止:企業の経理業務において、不正防止や監査対応のためにも領収書の保管は重要です。また、法人は原則7年間、個人事業主は原則5年間の保管義務があります。電子帳簿保存法に基づき、電子データとして保管するケースも増えています。
なお、納品書は領収書の代わりにはなりません。支払いの事実を証明できるものとしては、レシートや振込明細書などもありますが、税務調査の際に正式な証憑として認められない可能性もあるため、必ず領収書を受け取って保管することが望ましいでしょう。
納品書や請求書の電子化が進む背景
-
近年、企業の間で「納品書」や「請求書」をはじめとする取引書類の電子化が急速に進んでいます。その背景には、法改正への対応だけでなく、コスト削減やリモートワークの普及、そしてセキュリティ強化といった多様な要因があります。
ここでは、それぞれの観点から電子化が進む理由を解説します。
法改正への対応
-
まず大きな要因となっているのが、法改正への対応です。
2022年1月の改正「電子帳簿保存法」により、電子取引で授受したデータ(PDF請求書や電子メールでの見積書など)は、電子データのまま保存することが義務化されました。猶予期間を経て、2024年1月1日以降は完全義務化され、紙に印刷して保存する方法では認められなくなっています。
さらに、2023年10月に始まったインボイス制度も電子化を後押ししています。適格請求書発行事業者として登録している企業は、取引先に対してインボイスを発行する必要があり、電子インボイスの仕組みを導入することで、制度対応を効率的に進められるようになります。これらの制度改正が、企業の電子化推進を強力に後押ししているのです。
コスト削減
-
電子化のもう一つの大きなメリットが、コスト削減です。
紙の書類を扱う場合、印刷用紙・インク代・郵送費などの物理的コストが発生します。また、保管スペースを確保するためのコストも無視できません。電子化すれば、こうした費用を大幅に削減できます。
さらに、人的コストの削減効果も大きいです。印刷・封入・郵送・ファイリングといった手作業をなくすことで、経理担当者の業務負担を軽減し、より生産的な業務に時間を使えるようになります。
リモートワークの普及
-
コロナ禍をきっかけに、リモートワークやハイブリッドワークが一般化したことも電子化を後押ししています。
電子化された納品書や請求書は、インターネット環境があれば場所を問わず作成・送付・確認が可能です。オフィスに出社しなくても経理業務を進められるため、働き方の柔軟性が大幅に向上します。
従来、紙の処理のために出社が必要だった経理担当者も、電子書類の運用によって在宅で完結できるようになり、業務効率の改善につながっています。
セキュリティ強化
-
セキュリティ強化の観点も納品書や請求書の電子化が進む背景の一つです。紙の書類は紛失・盗難・情報漏洩といった物理的リスクを伴いますが、電子化された書類はアクセス制御や暗号化により、安全性を高められます。特にクラウド型のシステムを導入すれば、データを安全に共有・保管でき、権限のある担当者だけが閲覧できるように設定できます。
また、電子データは災害リスクへの対策としても有効です。地震や火災によって紙の書類が失われても、クラウド上に保存されたデータは消失しません。これにより、事業継続性(BCP)を確保する手段としても注目されています。
まとめ
-
本記事では、納品書・請求書の役割や違いをはじめ、見積書・領収書など「取引書類の4大書類」の意義、さらに電子化の背景について解説してきました。正確な書類の運用と適切な電子化は、業務効率と取引の信頼性を高める必須の要素です。
取引書類の管理を効率化したいなら、クラウド販売管理システム「s-flow」の導入もおすすめです。s-flowは販売・在庫・入出金管理といった業務を総合的にサポートし、見積書・納品書・請求書をPDFで作成・メール送信できる他、請求書の一括発行や出荷指示の自動化などを実現します。
初期費用ゼロ、月額4,800円〜というライトプランも用意されており、小規模事業者でも導入しやすい点も魅力です。無料でお試しいただくこともできますので、まずはお気軽にご相談ください。

- クラウド販売管理システム【s-flow】コラム編集部
- s-flowのコラムでは、販売管理・受発注管理・在庫管理・入出金管理をはじめとした各業務や管理に関連する「お役立ち情報」をご紹介しております!








